脳のパフォーマンスは感情次第

はじめに
頭痛について勉強しているうちに、脳にも興味が湧いてきました。
脳の特性を知ることで、頭痛の改善に役立つことも多々あるような気がします。
人が本来もっている本能や脳の癖を知ることで、毎日を快適に生きるヒントが見つかれば嬉しいです。
マイナスの感情はもつな
人間の目や耳から入った情報は神経回路を通りますが、脳内で考える仕組みが働く前に、まずは「好き」「嫌い」「感動した」などのレッテルが付加されます。
その後、脳が「理解」したり「思考」したりします。
この好き嫌いの「感情」がさきに付加されることで、その後のパフォーマンスが左右されます。
マイナスのレッテルをはられた情報は、しっかり理解できず、思考は深まらず、記憶もしにくくなってしまいます。
英語が苦手、数字が嫌いなど、一度マイナスなイメージがつくと脳は「嫌い」というレッテルが貼られているので、脳はその情報に関して積極的に動かなくなります。
脳の理解力や思考力、記憶力を高めるには、まず「おもしろい」「好きだ」というレッテルをはらなければなりません。
「好きになる力」を養うことは、そのまま「頭をよくすること」でもあるといえます。

先生を嫌うと成績が下がる
子供の頃、嫌いな先生が教える科目は成績が伸びなかったという経験はありませんか?
先生や上司が嫌いだと「嫌いだ」というレッテルをはります。
「先生が嫌い」「上司が嫌い」などと人を嫌悪するのは、大切な情報にマイナスのレッテルをはってしまう習慣なのです。
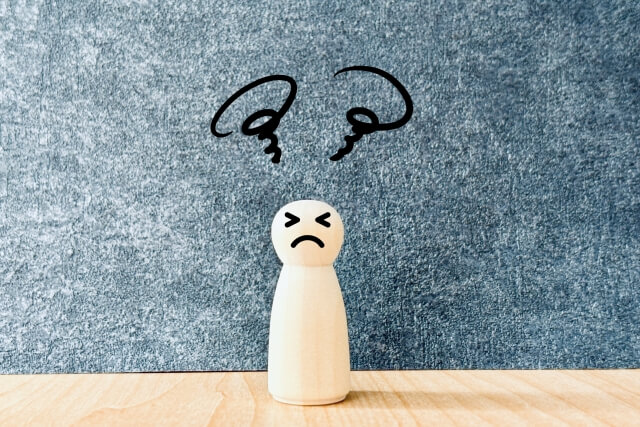
そもそもなぜ人はなぜ他人を嫌いになるのでしょうか?
その理由は【脳の3つのクセ】で紹介した「自己保存」と「統一・一貫性」にあります。
「統一・一貫性」という脳のクセから、人間は整ったものやバランスのよい物を好む傾向があります。
顔やスタイル、話し方などが自分の基準と大きくずれていると、それだけで拒絶したくなります。
また、自分と反対の意見を言う人を嫌いになるのも脳のクセです。
「統一・一貫性」のクセから、自分と違う意見は受け入れにくく、また「自己保存」が働くことで「嫌いだから避けよう」となるのです。
こうしたクセを抑えるには、まず「こういう人は苦手、嫌い」といった先入観を取り払うよう、意識することが大切です。
常に「人柄を知っていいところを見つけよう」という姿勢をもち、最初から「きっと好感をもてるだろう」と考えて話を聞くことが、脳にとっていい結果をもたらします。
「嫌だ」「疲れた」と口にするリスク
日常的に「無理だろう」「難しい」といった否定的な言葉を使う場面はよくあるはずです。
こうした言葉を発言するのも、実は「自己保存」という脳のクセの表れなのです。
このことに気づいていないために、「グチを言った方がストレス発散になるんだ」と誤解している人もいるのではないでしょうか。
ところが、こうした否定的な言葉は、自分が言っても、周囲が言うのを聞いても、脳にとっては悪い影響しかないのです。
というのも、目の前にやるべきことがあっても、否定的な言葉を聞くと神経群がそれに反応し、情報にマイナスのレッテルをはってしまうからです。
これでは、脳の理解力や思考力が落ちてしまいます。
何気なく口にする、そのちょっとした言葉がみなさんの脳のパフォーマンスを落としているとしたら、非常にもったいない事だと思いませんか?
しかもグチから何か新しい発想が生まれることはまずありません。
特に、仕事や勉強に取り掛かる前にグチを言うのは避けるべきです。
