思考を深めるには

はじめに
頭痛について勉強しているうちに、脳にも興味が湧いてきました。
脳の特性を知ることで、頭痛の改善に役立つことも多々あるような気がします。
人が本来もっている本能や脳の癖を知ることで、毎日を快適に生きるヒントが見つかれば嬉しいです。
効率を考えると思考が深まらない
何でも効率重視な昨今ですが、脳の仕組みから言えば効率重視の考え方は必ずしも正しくありません。
人間の思考とは繰り返し考えることによって高まるものであり、すばらしい考え、独創的なアイデアや新たな発見は、何度も何度も思考する事によって生まれます。
これは思考の繰り返しによって磨かれたアイデアと単なる思い付きが、意義や完成度においてまったく別ものであることを考えてもよくわかります。
もちろん、繰り返し考えるといっても、回数をこなせばいいわけではありません。
適当に考えるのではなく、綿密に理論の隙間がないように詰めていく必要があります。
隙間を見つけたら、そこを埋めるように吟味するのです。
何度も繰り返すと、それまで常識だと思い込んでいたことに対して「もしや」という思いが生まれることがあります。
もちろん、これは見境なく常識を疑う事ではありません。
大切なのは、綿密に繰り返し考えることで隙間が見え、それによって常識の誤りに気づいたうえで、その常識を打ち破るという思考の過程です。
このように思考を繰り返すことで、脳波斬新なアイデアや発見を生み出していきます。
昨今は、効率性が過剰に重視され、繰り返し考え吟味することを無駄と考える風潮があるようです。
しかし、効率だけを求めていては独創性は生まれません。
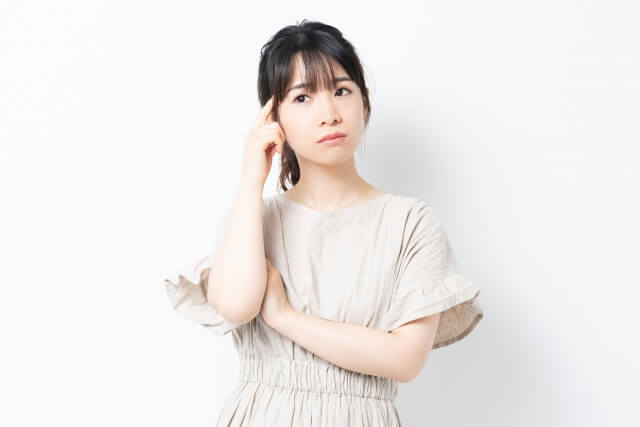
自分の意見にこだわるのはNG
「自分の意見は絶対に正しい!」と思うことはありませんか?
実はそれは脳の悪い癖の表れかもしれません。
頑固者で一度決めたら他人が何と言おうと自分の意見は絶対に曲げないというタイプの人は要注意です。
頑固さというのは、ときに「こだわりのある人」「意志の強い人」といったニュアンスで肯定的にとらえられることもあります。
しかし、ほかの意見を取り入れる余地がないほど一つの考えに固執し、「これが絶対に正しいはず」と思ってしまったら、それは脳の悪いクセが出ている証拠です。
「統一・一貫性」のために頑固になり、一旦正しいと思い込んでしまうと、脳はそれ以上思考を深められなくなるのです。
人間の脳が持つ「統一・一貫性」のクセをはずすには、物事を考えるときに「自分を疑う」という視点を持ち込む必要があります。
言うのは簡単でもなかなかできないものですが、これはそもそも「統一・一貫性」が理論的な整合性判断に必要な作用で、人間の思考の基盤をなしていることに理由があります。
しかし、意識的にこの基盤をはずさなければ、独創的な思考は生まれません。
世の中で独創的だと言われる人が少なく、重宝される傾向にあるのは、それだけ「統一・一貫性」のをはずすのが難しいことを示していると言えるでしょう。
「統一・一貫性」のが思考に与える影響を理解すれば、問題に対処する力をつけることは可能です。
思考を深める際は「統一・一貫性」のクセに縛られていないか?と冷静かつ客観的に検証するスタンスを持つようにしましょう。
