肩こり・首こりをわかりやすく徹底解析!

目次
日本人と肩こり・首こり
厚生労働省の調査によると、全国民のうち男性の約6パーセント、女性の約13パーセントが「肩こり」を訴えており、この割合は全ての症状の中で男性は第2位、女性は第1位となっています。
首や肩に症状があっても病院やクリニックを受診せず、とりあえず首や肩の筋肉を揉んだり、首や肩の関節を動かしたりするという方は少なくありません。
こうした行為は、時として症状が緩和する場合もあり、決して悪いわけではありません。
しかし、むやみに筋肉を揉み、関節を動かしたためかえって症状が悪化した経験がある方も少なくないと思います。
つまり、多くの方が、症状が良くなることも悪くなることも頭では理解しながら、筋肉を触り関節を動かすことを繰り返しているわけです。
しかし肩や首には筋肉や関節だけでなく、重要な血管や神経が多数存在しています。
間違ったやり方を繰り返した結果、からだの組織を破壊してしまい、二度と改善しえない大きな障害を生んでしまう危険性もあります。
首や肩の構造や機能を理解できれば、首や肩を触り動かすうえで危険なことと安全なことの線引きができ無理なく肩こりや首こりから解放されることでしょう。
肩こり、首こりから頭痛を引きおこし、会社や学校をはじめ通常の生活に支障をきたしている方も多くいらっしゃいます。
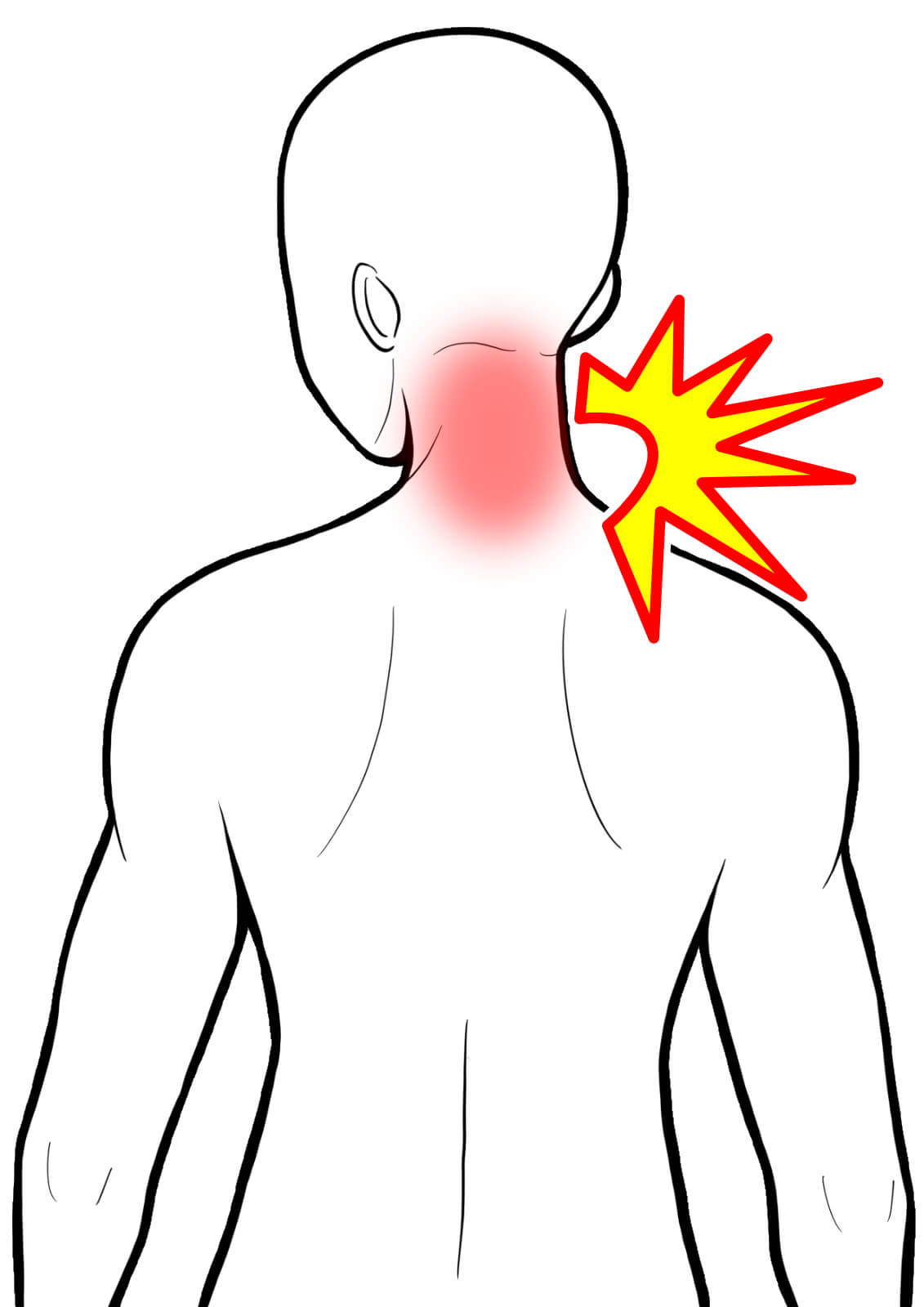
首の役割
首のもつ役割を知ることで、首の大切さを理解できます。
首の役割その1「頭を支える」
頭は体重の10~15パーセントの重さがあると言われ、体重が60キロの人であれば6~8キロの重さになります。
首にはこの頭を支える役割があります。
首の役割その2「視覚の調節」
頭には目がついていますので、体を動かしたときに頭が大きく動いてしまうと、視覚情報が一定しません。
そこで首は、どのような状況でも頭を一定の位置に保つよう調整に動いています。
正確には首についている筋肉がその役割を担っているとされています。
首の役割その3「寝返りや起き上がりの調節」
首は背骨のなかで非常によく動きますが、この首の動きにより、人はベッドや布団に寝ている状況から、楽に起き上がることができます。
首を横に向けなければ、とたんに起きにくくなります。
寝違いを経験した人なら寝返りをうとうとしても、首が痛くて動かないと寝返りがうてないのを経験したことがあると思います。
首の役割その4「その他の役割」
首には脳へ血液を供給する血管が通っており、重要な血管の通り道としての役割も担っています。
また、両手で何かものを扱う場合には、首はその基軸としての役割を担います。
このように首には様々な役割があり、私たちは無意識のうちに普段の生活のなかで首を多用しています。
肩の役割ポイント
大人なら5キロ以上はある頭を細い首だけで支えています。
重力でたえず下へ落ちる力が働いている首を、常に首周りの筋肉が抵抗しているのです。
それだけでも大変なのにストレートネックと言われる前に頭が落ちてしまう状態になると、首にかかる負担は相当なものです。
スマホを見る姿勢に頭を前に落とすと首・肩へかかる負荷は27キロとも言われれています。
小学校1年生をずっと首からしがみつかせておんぶしているような負担を体にかけているのです。
ストレートネックについて詳しく知りたい方はこちら⇒
首の長い人と短い人の違い
首が長く見える人と短く見える人がいますが、このことを首の構造から考えてみましょう。
首の骨は専門用語で「頸椎」と言います。
頸椎は全部で7個存在し、上位より数えて1番、2番と呼びます。
頸椎が7個というのは哺乳類すべてに共通していて、首の長いキリンや首の骨がないように見えるクジラも同じです。
それではなぜ首が長く見えたり、短く見えたりするのでしょう?
理由は鎖骨と肩甲骨の位置にあります。
私たちは「なで肩」や「いかり肩」で表現されるように鎖骨と肩甲骨の位置で肩の高さを判断しています。
そのため鎖骨や肩甲骨の位置が下がると相対的に首が長く見えるのです。
首からくる頭痛に悩まされている方は一度ご相談ください⇒
